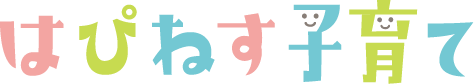サポートの実施方法
発達障害を持つ子の中には、お友達のことを叩いてしまったり、突き飛ばしてしまったり、手が出てしまったり・・また、先生の腕に噛みついたり、怒って物を投げて壊してしまったりと、いわゆる「他害(たがい)」と言われる行動 をしてしまうケースがあります。
「他害行動」をしてしまう子のサポート方法について、ポイントは下記になります。
大人がその場に居合わせること
(=手が出る前の様子がわかる+手が出る前に関われる)
- 手を出す前に関わって、望ましくない経験を繰り返させない
- 本人の思い・考え・意志を大事にして、やり取りを成長につなげていく
- 可能であれば、子供同士の関係をより良いものにしていく(お互いの理解などを促しながら)
大人が「子供の状況」にアンテナを張りつつ、見守る。
「子供の手が出る前」に関わって、成長につなげる。
他害のことに取り組む時、大事なのは?
- 『子供の手が出てしまう前に対応する』
- 『目的は、他害を無くすことではなく、子供の成長を促すこと』
他害に関して、実際の変化は?
「子供の手が出る前」の段階で、子供の思い、考え、欲求を見つけ、その方向にサポートをする。子供の「その部分」が成長すると、結果的に手を出す必要がなくなる(他害がなくなる)という変化が表れます。

ケーススタディ(実際の事例)

今回登場するのは、小学3年生の女の子『D子ちゃん』。ADHD(多動型)の診断があり、特別支援学級*に通っています。保育園の頃から、先生の腕を噛んだり、友達を引っかいてしまう「他害行動」がありました。
- 特別支援学級とは、教育上特別な支援を必要とする児童および生徒のために置かれる学校学級です。
「他害行動」に関して、本人の感覚は「困った末に、言葉で表すこともできず、必死になってやってしまっただけ…」ということなので、大人から「引っかいてはダメ!」と注意されても「自分が悪い」と思うことができませんでした。
『D子ちゃん』へのサポート活動の開始
『D子ちゃん』へのサポートにあたり、まずは近くにいること、 “普段の様子” を見ながら、本人の思い、意志を探してみることにしました。
お友達と合流したく『D子ちゃん』は、女の子2人で「ごっこ遊び」を始めました。
「英語の先生」と「生徒役」に「アルファベットの授業ごっこ」です。
(ごっこ遊び中の会話)
D子ちゃん「コレは”A”という文字、そして次の文字は”B”です。わかりますか?」
友達のE子ちゃん「ハ~イ、わかりました♪」
そして、お友達が、ペンを取りにその場を離れようとした瞬間、
『D子ちゃん』は慌てて「ダメっ! こっち!」と急に強い口調になりました。お友達の腕を「グッ!」と掴んで離そうとしません。(この状態は「”他害行動” か “そうでないか” の境界線ぐらいの感じです)
『D子ちゃん』は、自分の気持ちをどう言葉にしていいかわからない状態」で、ただ黙って腕を「ギュッ!」と掴んだままです。お友達のE子ちゃんも困ってしまい、今にも泣き出しそうな顔に・・。

『D子ちゃん』の気持ちをヒアリング
ここで、大人が介入します。『D子ちゃん』はまだ「自分の言葉での説明」がうまくできないので、大人の側で「本人の気持ち・考え」を察しながら、丁寧に状況を聞いていきます。
彩先生:「嫌な気持ちになったの?」
D子ちゃん:「… ((本人考え中 )) 」
(本人に聞いていく時は、急かさず、たっぷりと時間をとります)
彩先生:「お友達のE子ちゃんが離れるのが、嫌だった?」
D子ちゃん:「… ((本人考え中 )) 」
(本人は、いろいろ考えている最中のようです)
彩先生:「E子ちゃんに、ここにいてほしかったの?」
D子ちゃん:「…一緒に遊びたかった・・」
(この様に “本人の気持ちに合う言葉” を見つけられると大きなプラスです)
このやり取り、もちろんE子ちゃんも一緒に聞いていて、D子ちゃんの気持ちを知ったE子ちゃんは「平気だよ!ペン取ってくるだけだよ♪」と言葉をかけてくれました。『D子ちゃん』は「ホッ」と、ひと安心の様子。そして、また2人で「ごっこ遊び」へと戻っていきました。
サポート活動の続き
『D子ちゃん』へのサポート活動は続きます。
『D子ちゃん』と “この様なやり取り” を20回ほど重ね、本人の気持ち・考えなどを聞いていきました。
他害への取り組み、サポートを行う際のポイントと目的は、
「他害をなくすことではなく、本人の成長を促すこと」です。
そして、その「本人の成長を促す」ためには、 はぴねすメソッドのコーナーで紹介している基本項目『本人の気持ち・考え・意志を大事に』という方針で “やり取り” をしていくことが重要になります。
こうした “やり取り” を重ねていくうちに『D子ちゃん』の中には、
「とにかく、お友達と仲良く遊びたい!」
「自分が知っている “いいこと” を友達に教えてあげたい!」
「自分が教えてあげている時は “自分の気持ち” もちゃんと受け取ってほしい!」
という気持ち、そして、
「自分が “一人” になっちゃうのは不安・・」
「自分が “置いてけぼり” になるのが嫌・・」
という思いがあることがわかりました。
『D子ちゃん』本人の欲求=「お友達と仲良く遊びたい!」
というものでした。
「子供の手が出てしまう前」にある、本人の欲求を見つけること、ここまでがサポートの第一段階ということになります。
この先、本人が進みたい方向である「お友達と仲良く遊べるように!」という方針でサポートを行っていきます。

その後のD子ちゃんへのサポートの様子を紹介します。
やり取りを重ねて見つけた、本人が進みたい方向 =「お友達と仲良く遊べるように!」という方針でのサポートです。
『D子ちゃん』への提案(サポート実例の会話)
たとえば「『D子ちゃん』と一緒に遊んでいたお友達が、その場から離れてしまいそうな時」、この様に話しかけました。
彩先生:「『D子ちゃん』、『私もついて行っていい?』と聞いてみたら?」「『お友達と一緒に行ってみる』のはどう?」
D子ちゃん:「うん・・」
⇒すると『D子ちゃん』はすぐに「トライ」。1回やってみただけで、お友達との新しいやり取りの方法を身に付けました。
そして、「お友達が『D子ちゃん』と違う遊びをやり始めて、不安になっている時」には、この様に話かけました。
彩先生:「今、『D子ちゃん』がやってる遊び、続きは後でもできそうだよ♪」、「お友達がやっている遊び、一緒にやって来たら?」
D子ちゃん:「うん・・」
⇒すると『D子ちゃん』、「じゃ、続きは後でやる!」と言って、皆に合流することができました。
( “本人の不安が高まりそうな時”に、 声をかけてあげることが大切です)
また『D子ちゃん』は、遊びの終了時間が来ても、やめずに続けようとすることが多かったのですが、お友達とのやり取りが増えていくにつれ、安心感が増したのか、
D子ちゃん:「E子ちゃん、学校ごっこまたやろうね!」
お友達:「うん、いいよ!」
などのやり取りで、キリよく活動を終わることができるようになりました。
こうして『Dちゃん』が困っていた 、 “どうしていいかわからない不安”が減っていきました。
以前のように「誰かの腕を、強引に引っ張って引き留める」必要もなくなり、「他害らしきもの」は無くなりました。
(この頃、サポートの開始から3ヶ月ほどが経過していました)
それからの『D子ちゃん』。
『D子ちゃん』、実はダンスが得意です。「お友達用の振付」など考えてきて皆に教えてあげたり、その様子を見ていた「一緒にやりたそうな子」には「一緒にやろう♪ こっちにおいで!」など、とても友好的な対応を取るようになりました。もともとあった「お友達と仲良く遊びたい気持ち」をお互いにとってよい形で発揮できるようになっていきました。
他にも「髪飾り」のアクセサリーを作っては、お友達につけてあげたり、お友達をお世話するのも楽しい感じ、まるで「親切な、みんなの先生」の様な活躍をするようになりました♪

今回のサポートポイント
まずは基本中の基本である
- 「活動する場面に一緒にいる」
- 「”本人の様子” がわかるように、”手が出る前” に関われるようにする」
というスタイルでサポート。
今回の『D子ちゃん』の場合「本人が困ってから、行動に移るまでの速度」がとても速かったため、かなり近くで見守るスタイルのサポートにしてみました。
事あるごとに「本人の気持ち・考え・意志」を聞いてみて、本人の「お友達と仲良く遊んでいたい!」という欲求を発見。
そして「この方向」でのサポートを実施。「他害」そのものを扱うのではなく、手が出てしまう前に「本人の気持ちが向かっている方向」へサポートです。
今回の活動では、子供本人が困ったり、不安そうになったらすぐに大人が介入し、 そして「どう言えば」、「どんなやり取りをすれば」、お友達と仲良く遊べそうかを提案しながら、その場で実施していきました。
そして、子供同士のよい関係を保ちつつ「仲間たちの成長」も一緒にサポート。
結果的に、「どんな時に、どんな風に言えばいいか」を「実際の遊びの場面」でいくつも身につけることができました。
おわりに
『D子ちゃん』の仲間に対する想い、そして仲間に「教えてあげたいこと」が、相手に伝えられるようになっていき、本人の意欲も倍増、自信にもつながったようです。
喋る量、笑う量も格段に増え、皆の前で「杖をついて歩くお爺さんのモノマネ」を披露し「お友達を笑わせる」などの行動も見られるようになりました。
その後も『D子ちゃん』の「仲間想いは」ずっと変わらず・・
たとえば、引越しで “離ればなれ” になってしまったお友達には、マメに手紙を書いたりして、自分の気持ちを伝えたり、夢を語りあったりもしています。
(そのお友達とは、大人になったら一緒に暮らしたいそうです♪ この素敵な夢は、双方の親御さんからも応援されています♪)

\ お便り応募フォームはこちら /