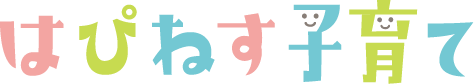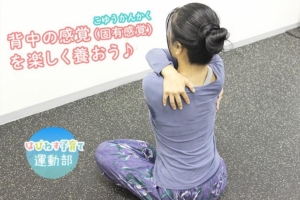みなさんこんにちは、はぴねす子育てトレーナーの坂本です。
「はぴねす子育て」運動部では、お子さま一人ひとりが持つ可能性の土台作りになる「運動」や「感覚」に対する働きかけを、専任の認定トレーナーからご紹介しています。
今回のエクササイズは「裸足(はだし)歩き」です。とっても簡単なので、ぜひやってみてくださいね♪

足裏の感覚を養い全身を元気に!「裸足(はだし)歩き」のススメ
みなさんには「裸足(はだし)」で生活する時間はありますか?
たとえば、歩く時を考えてみます。
- 平らに舗装(ほそう)された “アスファルトの上” を、底の厚いクッション性の効いたスニーカーで歩く。
(固いアスファルトの衝撃を吸収してくれるので、これはこれで大切です) - お部屋の中でも、靴下やスリッパを履いている。
こんな「地面からだいぶ離れた生活」をしていないでしょうか?
もし「1日の中で、裸足になるときは?」と聞かれたら・・
「お風呂の時と、眠る時だけ・・」という方も多いかもしれませんね。
二足歩行の私たちにとって、足裏はとっても大切な機能がたくさんあります。

「足の骨」について考えてみよう
みなさんの体を支える「足の裏」。
いったい足にはどれくらいの骨があるか知っていますか?
答えはなんと「56個」!(両足で)
細かく見ていくと、まず後足部の『足根骨(そくこんこつ)が7個』、『中足骨(ちゅうそくこつ)が5個』、そして前足部の『趾骨(しこつ)が14個』、さらに『種子骨(しゅしこつ)が2個』で合計28個もあります!
身体の全身の骨は「約200個」ですから、足の骨だけで「1/4」を占めていることになります。
両足で「56個」もの骨が、みなさんの身体と動作を支えています。
このたくさんある骨が色々な動きをしてくれるから、私たちは、歩いたり、走ったり、登ったり、ジャンプしたり「あらゆる動き」が安全にできるのです!
身体の健康にかかわる「足の裏」
「足の裏」には、骨だけでなく「たくさんの筋肉」がありますが「感覚」もとても豊か。
「第2の心臓」と呼ばれるほど、多くの情報を脳に届け、全身に指令を送る大事な役割を担っています。
そのため「足の裏」の機能がしっかり活かせているか?によって「身体の支え」、「神経伝達」、「運動機能」に多くの影響が出てきてしまいます。
たとえば足の状態が
- 土踏まずが浅い・・(扁平足:へんぺいそく)
- 足の甲が高いまま固まっている・・(甲高:こうだか)
などの場合、疲れやすくなったり、すぐに座りたくなってしまったり、首や腰に負担が来ることもあります。
この様な足の状態の解消には『タオルギャザー』と呼ばれるトレーニング(床にひろげたタオルの端に足のかかとを合わせ、足の指でタオルをたぐり寄せる運動)もありますが、今日はもっと簡単で、もっともっと楽しく「足裏が賢くなる方法」をご紹介します♪
足裏の感覚を養い全身を元気に!「自然の大地を “裸足” で歩く」
その1
公園の砂場、土、砂利、お庭の芝生の上などを「裸足」で歩いてみましょう。

その2
その時、砂を「足の指」で掴んだり、土を「足の指」に挟んだりしてみましょう。

たったこれだけです!
(もし海辺の砂浜などの場合は、走ったりするのも良いですね♪)
「裸足」で自然を歩くだけで「足の裏」が様々な地面の情報(土なのか、砂利なのか、砂なのかなど)を察知し、脳へ信号を送ります。そして、それに対応した「筋出力」を全身に出してくれる様になります。
「身体の支え」、「神経伝達」、「運動機能」において重要なこの一連のプロセスが、裸足で自然を歩くだけで、簡単に実現できてしまうんです。
※いつも平らな場所で生活していると、この大切な感覚を養うことがしにくくなるため「足の裏」の大事な機能が「活かせていない状態」となってしまいます。
- 「砂利の上」をあるくときは、慣れるまで「痛く」感じるかもしれません。その場合は公園の「砂場」など、まずは安全な「柔らかい地面」を選んで足裏と足指を使って、色々な動作を楽しんでみましょう。
- 「アスファルトの地面」はとても硬いので、裸足で歩くのは避けましょう。「関節」に負担をかけてしまう場合があります。

いかがでしたか?足裏の感覚を養って全身を元気にする「裸足(はだし)歩き」のススメ、とっても簡単なので、ぜひみなさんも気軽に試してみてください。
今回ご紹介した「自然の地面」以外にも、ぜひ安全で自然な場所を見つけて試してみてくださいね!
はぴねす子育て運動部では、これからも、みなさんが安心して取り組めて「子どもの運動への経験」を重ねてゆける「簡単エクササイズ」を発信していきます。
次回の記事もぜひお楽しみに♪