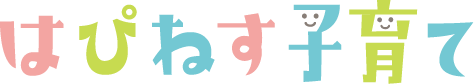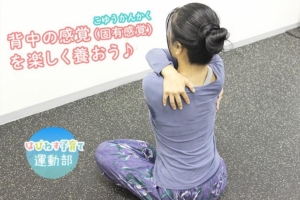“適応”や”訓練”よりも大事なこと
「子育て」や「子どもの成長」の内容を取り扱っていく際、子どもの環境への「適応」や、様々な環境に対応する「訓練」という言葉がよく出てきます。
まず、子どもの「適応」に関して一例を見てみましょう。
- 文字を書くときに「枠の中に字を収められる」様になる。
- 工作をするとき「ハサミを使ってまっすぐに切れる」様になる。
- 授業が始まってから「”45分くらい”はじっと座っていられる」様になる。
- 朝礼などで列を作る時「等間隔で並べる」様になる。
- “何か気になること”があっても「一旦踏みとどまって、質問せずに黙っていられる」様になる。
などなど。
ここで例にあげた「適応」。それぞれに意味があるのですが「何に適応しようとしているのか?」がとても重要です。
今回挙げた内容は、どれも「特定の状況(決められた枠組み)」に対しての「適応」であり、「特定の状況ではない場合」は「そうしない方がよいこと」も含まれています。
例えば授業中に、なんでもかんでも「出し抜けに質問すること」は「不適応」と思われてしまうことが多いですが、学校教育が終わり、大人になり「責任のある仕事」に就く頃には、
気になることがあったら、どんどん質問をした方がよい!
というようなことがあるわけです。
通常「特定の状況」への「適応」を目指して、学校や教育の現場では「指導」や「訓練」が行われていくのですが『はぴねす子育て』で大事にしているのは、もう少し「子どもたちの土台の部分」の成長になります。

『はぴねす子育ての視点」はこのようなものです。
「特定の状況」への「適応」よりも、それぞれの子が『どういう人間になっていくか?』を優先する。
具体的には、
- ★本人の興味・気になること(子ども本人の中にある基準)を大事にしていく
-
⇒「本人が自発的・主体的に動いていることの中には、必ず成長のタネがある」
参考ページ 「はぴねすメソッド」その3 【】 『はぴねすメソッド・その3』は、「子どもが”お気に入り”と感じる活動」、「子どもの趣味の世界」を見つけ、分かち合い、生かしていく。という内容です。たとえば…
「はぴねすメソッド」その3 【】 『はぴねすメソッド・その3』は、「子どもが”お気に入り”と感じる活動」、「子どもの趣味の世界」を見つけ、分かち合い、生かしていく。という内容です。たとえば… - ★子どもとのコミュニケーションを大事にしながら進む
-
⇒「気持ち、考え、楽しみを共有することは、本人の成長につながっている」
参考ページ 「はぴねすメソッド」その2 【子どもとの “やりとりそのもの” を大事に。】 『はぴねすメソッド:その2』は、子どもとのコミュニケーションを磨き、大切にする。子どもの思い、感じ方、意志を大事…
「はぴねすメソッド」その2 【子どもとの “やりとりそのもの” を大事に。】 『はぴねすメソッド:その2』は、子どもとのコミュニケーションを磨き、大切にする。子どもの思い、感じ方、意志を大事…
この様な部分を大事にしていった方が「子ども本人が自らが学べる」ことが多く「本人が自分自身の内側から学んでいること」は、身につきやすいものです。さらには「その子らしさ」、「その人らしさ」も育っていきます。
これまで関わってきた子どもたちの様子を見ても、学校を含めた「社会への適応」より、まずは
「本人の興味・気になること」を大事にコミュニケーションして「本人の人間としての成長」を優先していくこと。
この様に進んで行き、ある程度「本人が本人らしく成長」してから「社会への適応へ向かう」と、さまざまなことが「円滑に進んでいく」ということがあります。
\ お便り応募フォームはこちら /